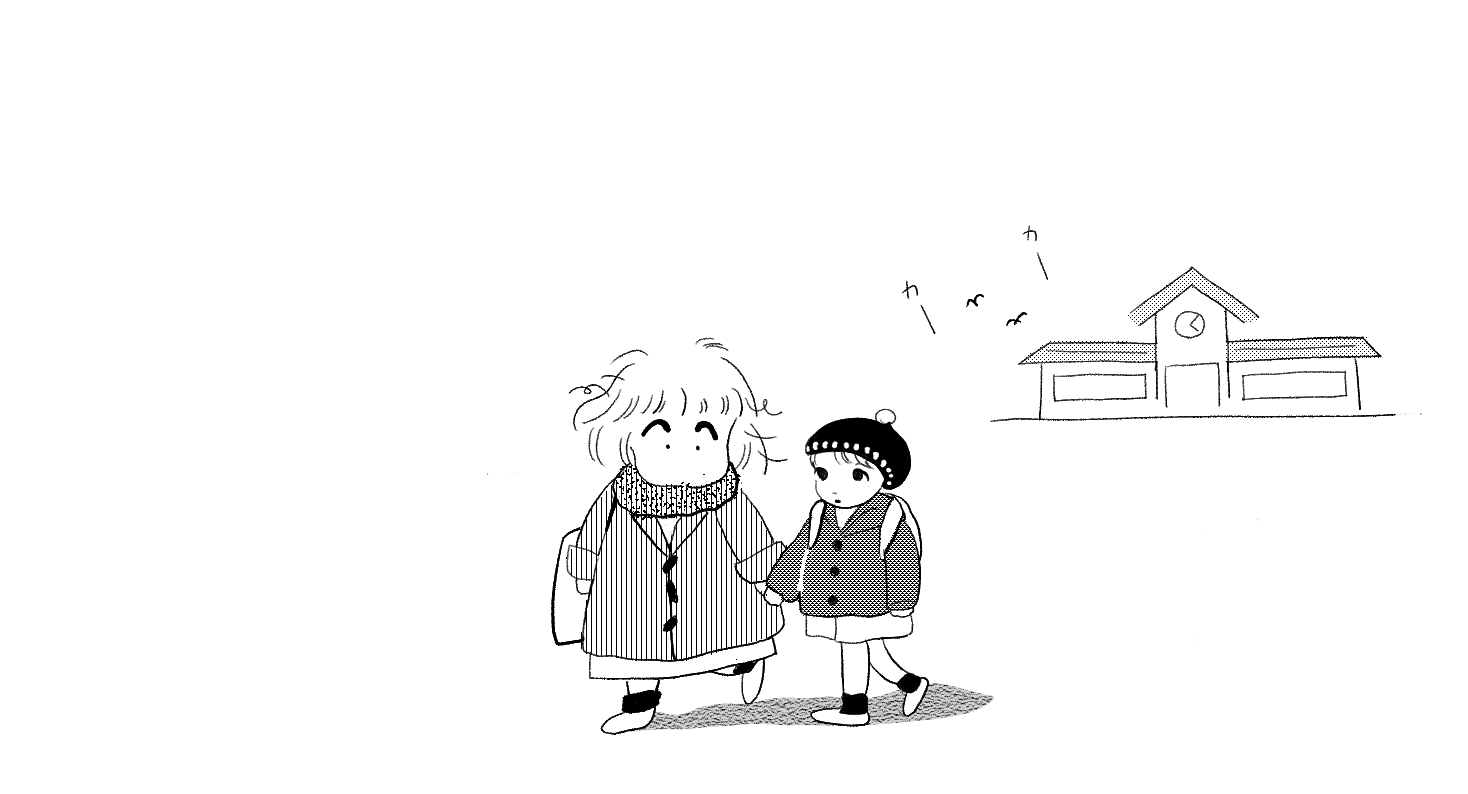どうも!千石おかんです。
今回は千石おかんが保育園選びで大切にしていることをご紹介したいと思います。。
前置き長いので、お時間ある方は気軽にご覧ください。
わたしは育児に関し、児童精神科医・佐々木正美さんの著書「子どもへのまなざし」を参考にしています。この本は、佐々木さんの臨床経験を踏まえ乳幼児期の育児の大切さを語る名著です。
私は最初、保育園選びは施設や園庭の大きさ、規模、家からの距離などを重点に考えていました。
もちろんこれらは大事なのですが、佐々木さんの著書を読み、乳幼児期はこころの豊かさを育む非常に重要な時期だと知り、目線が変わりました。
そして乳幼児期といっても、乳児期(0~1歳半)と幼児期(1歳半~4歳)で大切なポイントは違う。
今回は乳児期、幼児期の大切なポイント、そこから保育園選びにどのように繋げたかをお伝えします。
まず乳児期の保育は、子どもが望んだことを望んだとおりに応えてあげるのが非常に大事であると、佐々木さんは語られています。
なぜなら自分の要求が望みが叶えられた子は、自分が愛されている存在なんだと自信がもて、同時に他者を信頼でき、やがて成長すると自然と自立ができる子に育っていくからだそうです。
逆に、この時期に十分に自分の要求を満たしてもらえなかった子は、親への不信感、自分や世界への無力感をもち、大人になってからも自立できなかったり、何事も諦めてしまいやすい子どもに成長する傾向があるそうです。
そして重要なのは、乳幼児期を越えた後に、子どもの要求を満たそうとしてもやり直しをするというのは成長すればするほどに難しくなるということです。
建築でいえば、こころの土台の基礎をつくる乳幼児期こそ、嫌がらずに望んだとおりにしてあげる、これが最も大切だと、佐々木さんは語られています。
やがて幼児期に入ると、今度は自分からいろいろなことをやってみたいという意欲、自発性や主体性がでてきます。幼児期の子どもにとってまず大事なのは友だちと遊ぶこと、佐々木さんはこのように幼児期における友だちの大切さを語られています。
この時期の子どもたちは、必ずルールをつくって遊びます。みんなでルールをつくり、ルールを守り、仲間の承認を得て役割を演じ、責任を果たす、それがこの時期の子どもたちの遊び。
それらのプロセスを通して、自分を抑制することや、ふるまいを考え、自分自身や他者を理解していくからこそ、友だちは大事なのだそうです。
乳幼児期の親や友だちとのつながりが、なぜどのように大切なのか、児童精神科医の目線から見語られており、折にふれて読みたくなる出汁のある本だなと感じます。
では次に、これらを踏まえて保育園選びで自分が大事にしたいことは何かをお伝えします。
乳児期(0~1歳半)は子どもの要求を見逃さない環境
乳児期はできるだけ子どもの要求が見逃されにくい環境が良いなと思いました。
具体的には例えば決まった先生がつく担当制保育の園や、幼児の数に対して先生の配置人数が多い園、子どもの要求に常に応えられるこころの余裕や姿勢をもつ先生がいる園が良いと思っています。
担当制保育とは、決まった先生が子どもの担当になり世話をすることです。さまざまな先生がかわるがわる世話をするより、決まった先生に世話をしてもらうことによって、子どもとの愛着関係をより強く持つことができます。
幼児期(1歳半~5歳)は異年齢の子どもたちと一緒に遊び、好きなことを伸ばせる環境
幼児期ではいろんな年齢の子どもと友だちになる機会を得て、関係性を豊かにしていける環境、そして好きなことを伸ばしていけるような環境が良いなと考えています。
具体的には、異年齢制保育を取り入れてる園や園児の数があまり多くない園、子どもの意見を大事にしている園が良いなと思っています。
異年齢保育とは、年齢の異なる子どもでグループやクラスをつくることです。子どもの意見を大事にしている園かどうかは、方針ももちろんですが、見学に行ってみた時の先生方の発言や子どもと接している様子も観察しています。
以上のようなことを大事にしたいなと考えています。
他には家からの距離、施設や園庭の広さ、規模、荷物の負担が少ないところ、などを総合的に見ています。見学すればするほど、いろいろな違いも見えて来たり、迷う部分も出て来たり…。
あまり視察目線の気合が入ると疲れるので、子どもと地域の街を知るお散歩気分で見学にいくようにしています。
少しでも参考になれば嬉しいです。